シャワー上がりの濡れた髪をタオルで拭きながら、跡部は携帯端末を耳に押し当て、そっと目を閉じる。
『いいのか、跡部。お前も忙しいだろう』
そうすることで、聞こえてくる声が、全身に染み渡っていくようだった。
「いや、構わねえよ。だが……お前こそ本当に大丈夫なんだろうな?」
肘は、と続けてやった相手は、言わずもがな愛しい男だ。
手塚は全国大会決勝戦でまた無茶なプレイをした。そのゲーム自体は観戦できなかったが、越前リョーマを連れて戻った時に見た彼の腕は、痛々しい状態だったことを思い出す。
『問題ない』
「……てめぇの〝問題ない〟って言葉ほど信用ならねえもんはねぇなぁ?」
跡部は苦笑して肩を竦めた。肩を痛めた状態でチームメイトに止められつつもコートに出て、跡部と長い試合をした後に、リハビリへ向かった男が何を言うのか。
しかも、テニスがしたいだなんて。
「お前は本当にテニスが好きだな」
『……ああ、好きだ。それはお前も同じではないのか』
息を呑んだ。
手塚の声で『好きだ』という言葉を聞くことになるとは。うめきそうだった唇を噛んで、手のひらで覆った。
――――ちくしょう、なんて破壊力だよ……!
顔の熱が上がる。耳の中で、手塚の声がぐるぐると回った。
「そうだな、俺様も同じだぜ」
ゆっくりと息を吐いて手塚に返す。同じように『好きだ』とは言えなかった。
『跡部、明日』
「ああ、分かってる。テニスしようぜ、手塚」
向こうからホッとしたような吐息が聞こえる。明日の約束を取り付けて、跡部は通話を切った。
「……あぁ……、あー……――っくそ」
端末をベッドに放り投げて、ぐしゃぐしゃと髪をかき混ぜる。予想もしなかった出来事に、ドクンドクンと心臓が大きな音を立てていた。
腰に手を当て、深呼吸を繰り返す。項垂れて、何度も目を瞬く。視線を泳がせても、息を止めてみても、熱が治まりそうになかった。
跡部はベッドに放り投げた端末を振り向き、困ったように眉を寄せる。
躊躇う気持ちはあったが、やがて、負けた。
ベッドに腰をかけ、ローブをそっとめくる。下着を緩やかに押し上げる物を目に認め、諦めたように息を吐いた。
手のひらで覆うように触れると、布越しにも熱が伝わってくる。吐く息も、それと同じように熱い。跡部は中へと手を忍ばせて、そのまま自分自身に指を絡めた。
「は、……っあ」
左手を選んでしまったのは、無意識だと思いたい。いや、無意識だからこそいけないのか。
これが手塚の左手だったら――なんて、そんなこと。
「んんっ……ぁ」
根元からしごき上げ、先端をこね回す。にちゅにちゅと淫猥な音を立てるそれが、浅ましい想いを跡部に知らしめてくる。
皮膚を撫で、形を確かめ、筋をなぞった。
は、は、と短い呼吸が空気を揺らす。じんわりと汗がにじんでくる。
せっかく入浴を済ませたのに、これでは意味がない。意味がないのに、今さら止められない。
「い……ッ、うぁ、あ……っ」
左手だけでは物足りなくなって、両手で自身を慰める。天井を仰ぎ、快感だけを追った。ふるふると首を振るのは、堪えきれない快楽のせいか、それとも後ろめたさからなのか。
「手塚、……てづかぁ……っ」
どうしても手塚のことを考えてしまう。初めて手塚に抱かれる夢を見た日から、何度も何度も、こうして自慰をしてきた。
そうして何食わぬ顔でテニスをするのだ。
手塚はそんなこと思いも寄らないだろう。肘は大丈夫なのかと心配して名を呼んだその口で、こんなに熱の籠もった欲を吐くなんて。
「あ、あ、っ……はあっ……あぁ」
背徳感で余計に快感が上乗せされる。ピンとつま先立った爪が、部屋のカーペットを掻いた。
鼻先からぽたりと汗が落ちる。びくびくと脚が揺れ、腰が沈む。のけぞった背を震わせ、断続的な声を上げて、跡部は自分の手のひらを汚した。
「あっ……あぁ……あ、はあ……んぅ」
荒い呼吸がだんだんと整っていく。そうするにつれて罪悪感がせり上がってきた。
何をしているんだ。
我に返ってしまえば、心やましいことこの上ない。
耳元で声を聞いたのがいけなかった。手塚が『好きだ』なんて口にしたのがいけなかった。
汚れを拭き取って、跡部は盛大にため息を吐く。年頃の男子が劣情を抱くことになんらおかしなことはないが、相手が相手だ。
明日も逢う男だというのが後ろめたさに拍車をかける。
――――そうだ、明日も逢えるってのに。
そしてそれ以上に、明日も手塚と逢えるということを嬉しいと感じてしまう自分を、情けなく思う。
全国大会が終わってからも、手塚とは頻繁に逢っていた。彼が言うように、多忙でないわけはないのにだ。
テニス部も次の世代に託さなくてはいけないし、生徒会の仕事もある。夏の大会が終わったからと言って、休んではいられない。それを抜いても、中等部を卒業したらイギリスに留学しなければならないのだから、やることはたんまりとある。
「イギリスか……」
テニスをしに行くのではない。もちろん部活動としてはできるだろうが、目下の目的は経済学の修得だ。いずれ跡部家を継ぐ者として、祖父から命じられている。
それに不満はない。幼少の頃から決まっていたことだ。そして、自分にならばできるという自負もある。祖父の期待を裏切ることはできない。
「……こんなところで、……こんなことで立ち止まってるわけにはいかねえんだがな」
だが未練はある。これまででいちばん情熱を注いできたものだ。だから手塚をテニスに誘うし、誘われれば何を置いてもイエスを返す。どこまでも高みを目指したい。自分にならできるという自信があった。
跡部はベッドに座ったままぐっと右手を上に伸ばす。ルームライトの光が、すぐそこにあるかのような錯覚を覚える。そんなわけはないのに、掴めるような気さえした。
「まったく困ったもんだぜ」
正直、あの男に出逢わなければ、このまま何の躊躇いもなく跡部家の後継者としての道を突き進んでいただろう。
だけど出逢ってしまった。
あの試合の時の情熱が、今もまだこの胸にくすぶっている。余計な感情をまとって、跡部景吾という体の中に住み着いてしまっている。魂を搦(から)め捕って、テニスという世界に縛り付けられてしまった。
『それはお前も同じではないのか』
手塚の声が、脳裏によみがえる。耳元で聞こえたあの声が。
「ああ……好きだぜ手塚。テニスも、お前も」
いつかは離れなければならないとしても、今はまだ、傍にいたい。
跡部の戦いは、静かに、密やかに、今も続いていた。
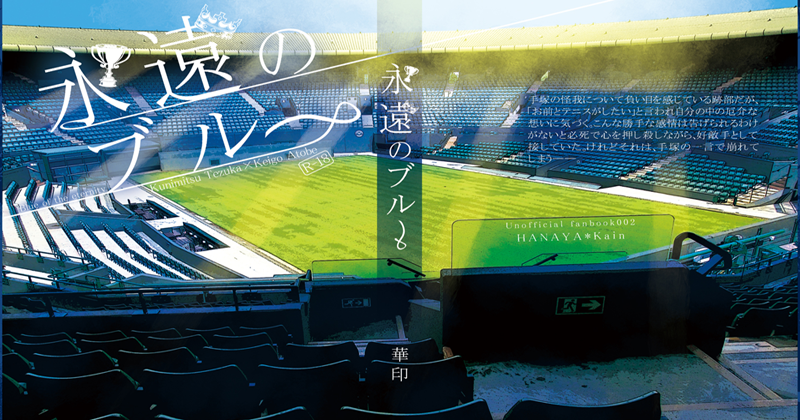
コメント