開催地域枠で、氷帝学園の全国大会出場が決まった。望んだ通りのストーリーではなかったが、上の大会に進めると意気込んでいるレギュラー陣を始め、二百名の部員たちや応援団の気持ちに水を差すわけにもいかない。
目指しているのは、高みだ。一個人のプライドやわだかまりで、潰してしまっていいチャンスなど存在しない。
「どいつもこいつも浮かれやがって」
夏休みだというのにわざわざ垂れ幕まで用意されてしまっては、受け入れるより他にない。跡部はパチンと指を鳴らし、騒がしさを蹴散らした。
「俺様とともに全国へついてきな!」
気分は、どうしても高揚してくる。終わったと思っていた夏の続きが始まるのだ。それは仕方がない。
全国大会は、強敵がたくさんいるだろう。レギュラーの強化やオーダーの相談、時間はあまり多くない。
跡部はすぐさま、練習を開始させた。大会出場が決まってテンションが最高潮にまで達した部員たちは、いつも以上に良い動きをしている。
「楽しみやなあ、全国」
「無様な試合しやがったら承知しねーぞ」
「せえへんわ、そんなん。これでもテンション上がってんねんから。謙也のとこも出るみたいやし」
いつでもわりととローテンションの忍足でさえ、珍しくテンションがだだ上がりらしい。そういうふうには見えないけれど。
「ああ、従兄弟だったか?」
「せや。四天宝寺、強いらしいで」
だが確かに、声のトーンが若干上がっている。眼力(インサイト)を使わずとも、忍足がわくわくしているらしいことが伝わってきた。従兄弟ということは、プレイスタイルも長所も短所も知っている相手ということだろう。
言うなれば、ライバル、だ。
跡部は、眉間に眉を寄せて目を細めた。
跡部の一方的な感情かもしれないが、彼は――ライバルだと思っているあの男は、間に合うのだろうか。
手塚の肩の状態が良くないという情報は、漏れ聞こえてこない。手塚の状態を気にしているのは跡部だけではなく、どうしてもそこかしこで囁かれているのだ。
リハビリは順調らしい、プロのチームが様子を見にいったらしい、向こうのプレイヤーをのしてしまったらしい、エトセトラ。
どれもこれもが噂の域を出ないものだが、その中には不思議とネガティブなものが存在しなかった。
誰も彼もが、手塚国光の復帰を願っている。
「跡部、今のうちに言うとくけどな」
「あん?」
「手塚が間に合わんかったら自分も試合には出えへんなんてのは、ナシやで」
少し高いところから降ってきた声に目を瞠り、忍足を振り仰いだ。彼は肩を竦めて半分冗談のように言っているけれど、九割が本心なのだろう。跡部はゆっくりと瞬いて、顔を正面に戻した。
「んなわけねえだろ、俺が出ねえでどうするんだ」
跡部としても、出場するなら狙うのは優勝のみだ。それは全校同じことで、他のレギュラー陣に任せっきりというわけにはいかない。頂点に君臨するキングとして、勝ちを見せてやるのも務めの一つだ。
「開催地枠だろうと関係ねえ。勝ちに行くぜ、忍足」
「当然や。誰が相手でもなあ」
跡部は太腿の横でぐっと拳を握る。目指すのは高み。そこに手塚がいようといまいと、強敵を打ち倒して君臨するのだ。
――――キングたれ、跡部景吾。
そう自らを鼓舞して、青い空を見上げる。
それでもあの日見た空ほど鮮やかではなかったけれど。
神奈川県、立海大附属中学の旧校舎に、跡部はいた。今日は全国大会トーナメント戦の組み合わせ抽選会だ。そこに、樺地を連れて氷帝学園テニス部部長として出席している。
会場を見渡せば、ジュニア選抜などで見知った顔がちらほら。どこの地区もさすがに強豪揃いだなと腕を組む。
――――青学は……大石か。
それでも、跡部がいちばん望んでいた顔はここにはない。
間に合わなかったのかと眉を寄せて目を細め、唇を引き結んだ。
手塚のリハビリが順調ならば、本来は彼がいるべき場所だ。部長代理として大石が来ているのは、つまりそういうことである。
手塚を欠いた状態で関東大会を制した青学は、純粋に称賛したい。立海すら押し退けるとは思わなかったが、個々のモチベーションを保つのも大変だったのではないだろうか。
いや、絶対に手塚を全国に連れていくという一つの意志が作用したのかもしれない。
だがここから先は、気持ち一つでどうにかなるものではない。
部を率いる将がいるのといないのとでは、大きな違いがある。精神的な支えとしてだ。
――――手塚、大会の途中からでも出られねえのか? そんなに……肩の調子、良くねえのか。
結局、手塚がリハビリをしている九州には一度も飛べなかった。逢いたい思いはあったが、合わせられる顔がない。今どんな状態でいるのかも分からない。
調べようか? と滝が声をかけてきたことはあったが、断った。そんなことをしている暇があるなら正レギュラーに戻ってこられるように精進しろと。
だが、いつまでも部員たちに気を遣わせているわけにもいかない。事実、今も隣で樺地が心配そうな瞳で見つめてきている。
この抽選会が終わったら、一度九州へ向かってみよう。万が一手塚と話すことができたなら、さっさと治してこねえと氷帝が全国をもらうぜと発破をかけてでもやろう。そろそろこちらも腹をくくらなければいけない。
進行係から、青学を呼ぶ声がする。よほど緊張しているのか、大石の耳には入っていないようだった。
「青学、東京都青春学園代表、いませんか!?」
「えっ、あ、は、はい! います!」
もう一度呼ばれて、ハッとした大石が顔を赤くやら青くやらしながら席を立つ。周りからは「緊張してやがるぜ」などと囃し立てる声が飛んだ。
抽選会からあの調子でどうするんだと、見ているこちらの方が不安を覚えてしまう。大石に部を任せていて大丈夫なのか? と眉間にしわが寄った。青学には何としても勝ち進んでもらわないといけないというのに。
もし手塚が間に合った時、戦う場所が在るように。
そしてできれば、もう一度相見えたい。個人としては戦えずとも、互いに高みを目指す場所にいたい。
その場所を潰してくれるなよと、責めるようにも、祈るようにも大石の動向を見守る。――はずだった。
「大石、それは俺に引かせてくれないか」
壇上へと向かいかける大石に、一つの声がかかる。
その声に会場の誰もが目を瞠った。無論、跡部もだ。
光の矢が己を貫いたような衝撃を覚え、声がした方を振り向けば、青学のジャージに身を包んだ――手塚国光がいた。
「……てづ、か……」
思わず、小さくその名を呟く。
会場のどよめきも、安堵と歓喜にまみれた大石の声も、跡部の耳には入らない。すうっと、凍り付いていた体が溶けていくような、妙な感覚を味わう。
――――手塚、間に合ったのか。
彼はいつもと変わらない様子でそこにいる。ふてぶてしささえ感じるほどの仏頂面で、無意識に周りを圧倒させるオーラを放ちながら。
ああ、……と、跡部はゆっくり息を吐き出す。それは間違いなく安堵で、自身もそう自覚していた。
ここにいるということは、少なくともテニスができる状態なのだ。良かったと、素直にそう思う。手塚ほどのプレイヤーを失わなくて本当に良かった。
そんな跡部に、ようやく会場内のざわめきが聞こえてくる。
あれが手塚か、プロも注目しているらしいぞ、だが怪我をしているんじゃなかったか、と。そんな中、何も気に留めない様子で手塚は壇上へと向かっていく。
「フン、手塚がなんぼのもんじゃい。ワシのスーパーテニスで――」
「やめとけ。テメェじゃ十五分ももたねえぜ」
身の程を知らないというのは哀れだなと、跡部は笑いながら諌める。同意を求めた樺地も、あまり間を置かずに「ウス」と返してきた。
性懲りもなく手塚の足を引っかけて恥をかかせてやろうとした輩がいたようだが、かわしたどころか「ずいぶん長い脚だな」と狙ってか無意識にか煽るような台詞を吐く手塚に、跡部は肩を震わせて笑った。
元気そうで何よりだと、壇上に上がった手塚を見やる。
ここに来るまでどれだけか辛酸を舐めたかもしれない。リハビリで心が折れかけたかもしれない。それでも手塚は戻ってきた。
また戦える。まだ高みを目指せる。
そうだ、あの男の諦めが悪いのは、跡部だってよく知っていたはずではないか。
気分が高揚してくる。テニスがしたくてウズウズしてくる。抽選会が終わったら即練習に向かいたい。
いや、その前にやるべきことがあった。
壇上から降りて大石のところへ向かう手塚を見やる。次いで組み合わせ表に視線を移し、青学とは準々決勝で当たることを確認した。
もう一度シングルス1で対決することになるだろうか。再び手塚を振り向いて思案するが、やがて跡部は苦笑した。それは少しばかり難しいかもしれないと。
あの男はふてぶてしくも氷帝に勝つためのオーダーを組んでくるはずだ。自身がシングルス1であることにこだわらずにだ。
それならば、こちらも絶対に勝つためのオーダーを組むだけである。跡部は隣に座る幼なじみをちらりと見やって、あらゆるパターンをシミュレートした。
何にしろ、まずはけじめをつけなければならない。
「樺地、今日は先に帰っていいぜ」
「……跡部、さん」
抽選会が終わって、各校の代表たちは会場を後にしていく。そう言って腰を上げた跡部を、幼なじみである樺地が心配そうに見つめてくる。この後、何をしようとしているのか分かっているのだろう。
「心配すんな。なにもケンカふっかけに行くわけじゃねえ」
ぽんと肩を叩いて笑ってやれば、樺地はこくりと頷いて会場を後にしていく。それでも心配そうに何度か振り向いてきたのは、しょうがないことだっただろうか。
跡部は息を吐き、廊下の壁にもたれる。
大石と何事か話し込んでいた手塚も、そろそろ出てくる頃かと、手持ち無沙汰な両手をポケットに突っ込んだ。
手塚が会場に入ってきて今この時点まで、視線は少しも重なっていない。あの試合の時は、世界で二人だけしかいないかのように視線で会話をしたというのにだ。
やはり良い感情は持たれていないのだなと俯く。
この期に及んで浅はかな期待をしても仕方ないなと、跡部はゆっくりと息を吐いて顔を上げる。
手塚はちょうど上機嫌の大石と出てくるところだった。跡部は壁にもたれていた体をゆっくりと起こす。
「手塚」
声をかければ、二人が足を止めて見やってきた。あの日以来の視線の交錯に、どうしてか跡部の胸が跳ねる。
「話がある。少し、いいか」
手塚は相変わらず表情を崩さないで、じっと見据えてくる。
その唇から拒絶が飛び出してくるかもしれないと思うと、らしくなく足が竦むような気分だ。
「ああ、構わない」
え、と驚愕が小さな音になる。持ちかけておいてなんだが、こうもすんなり受けてくれるとは思っていなかった。
「大石、すまないが竜崎先生への報告を任せてもいいだろうか」
「え、あ、ああ……いいけど、……大丈夫かい? 手塚」
大石の不安そうな視線が向かってくる。彼の懸念の方が、まだ理解ができた。
怪我の原因を作った相手と二人になって言い争いになったりしないだろうか――手塚が誰かと言い争う場面など想像できないが、一歩間違えば選手生命が絶たれていたのだ。心穏やかに話せるわけがないだろう。
「心配は無用だ」
「分かった。何かあったら連絡してくれよ」
こくりと頷いた手塚にどれだけか安心しつつも、大石は心配そうに何度か振り返りながら跡部を通り過ぎていった。
手塚が歩み寄ってきて、互いの間にあった距離が縮まる。跡部はじっと見つめてくる手塚の強い瞳を見つめ返して、口を開いた。
「肩、どうなんだ」
「治療は終わった。もともとそんなに酷いものではなかったのでな」
「どの口が言いやがる」
あんな試合をしておいて、と跡部は目を伏せて顔を背け、小さく舌を打つ。激痛に耐える表情を正面から見た跡部に、そんなごまかしは通用しない。
「いや、本当のことだ。どうも、心の方が重症だったようだが……イップスも克服してきた」
イップスと聞いて、跡部は目を瞠った。
肩が上がらないかもしれない。またあの激痛を味わうのかもしれない。ボールが打てなかったら、どうしたらいいのだろう。
早い話が、心的障害(トラウマ)だ。跡部は愕然とした。手塚ほどの男が、恐れたというのか。あんなに強い心を持っていながら。
そんな恐れを味わわせたのは自分だと、唇を引き結んだ。
そうして、ゆっくりと頭を下げる。
「悪かった」
自己満足だろうと何だろうと、そんな思いをさせたことは詫びたい。
「何の謝罪だ?」
少しの沈黙の後、手塚の声が降ってくる。
嫌みでなく、心底分からないといったような口調に、跡部は思わず顔を上げた。珍しく引きつった顔をだ。
「あぁ?」
「……跡部、まさかとは思うが、気にかけてくれていたのか。ずっと」
「なっ……てめ……、気にかけるだろうが、普通は! テメェの怪我は、元は俺がっ……」
あり得ないとでも言いたいのだろうか、この男は。腹が立って声が荒れる。行儀が悪いとは思いつつ手塚の左肩を指さしたが、手塚は強い瞳で押し返してきた。
「跡部、言っておくがこの怪我は俺の責任だ。俺が選択した結果だろう。お前には関係ない」
「――」
跡部の体が硬直した。関係ない――これは明確な拒絶だ。関わらせてもくれないのかと、全身が凍りつく。
「いや、関係ないというのは語弊があるな。お前に責任はないと言いたかった」
そんな跡部に気がついたのか、手塚がそう続けてくる。凍てつきが溶けた瞳で、跡部は手塚を見やった。
「……責任がねえわけねえだろ」
「ないと思うが」
「あるんだよ」
「ないと言っている」
同じ意味のことを繰り返し、平行線だ。跡部は得心がいかない様子で片眉を上げる。
「テメェ、そんなに頑固なヤツだったのかよ。いや……あのプレイからすりゃ分かるような気もするが。ともかくだ、テメェのその怪我は」
「お前が直接俺に何かしたわけではないだろう。もともとこれは俺が無意識に肘をかばっていたせいだ。そしてその肘の怪我にお前は関わっていない」
手塚は頑なだ。確かに直接敵には関わりがないかもしれないが、間接的には充分関わりがある。
償いもさせてくれないほど嫌われてしまったのだろうかと、気分が沈む。それでもプライドが、顔を背けることを許さなかった。
「……俺がテメェに対してできることはねえのか」
「肩はもう治っている」
「だが、リハビリのせいで練習時間は奪われただろう」
「それは仕方がない。跡部、本当に気にしないでくれ」
視線はお互いの真ん中で重なり合ったままだというのに、心が少しも重ならない。
それがもどかしくて、伝わらないことに腹が立つ。苛立たしげに目を細め、跡部は口にした。
「逆の立場だったら、テメェは気にせずにいられるのかよ」
その問いかけに手塚はわずかに目を瞠り、次いで眉を寄せた。それはそのまま答えとなったけれど、向けた瞳と同じほどの力を持った瞳が見返してくる。
「では逆の立場なら、お前は気に病んでほしいのか」
質問に質問で返してくるのはずるいと、跡部は舌を打つ。手塚もそれを答えと捉えたようだった。
逆の立場なら確かに、気にかけてくれるだけならまだしも、それを気に病まれるのは本意ではない。
「しかし跡部。そんなに心配したのなら、一度くらい顔を出してくれても良かったんじゃないか?」
「……アーン? 俺様が見舞いに行ってやらなかったからって拗ねてやがんのか、手塚ぁ?」
ため息交じりにやんわりと責められて、跡部は困惑する。
見舞いに行っても良かったのか――来てほしかったのか? と。
そんな困惑を隠すために、いつものようにふんぞり返って煽ってみせた。跳ねた胸のことは気に留めないようにして。
「……」
予想通り、手塚は面白くなさそうにわずかに眉を寄せる。そんなわけがないだろうという声が聞こえてきそうで、跡部はその愉快な光景にようやく自分を取り戻した。
「まあ、テメェがそう言うんだったら気にしねえようにしてやる。できるだけな。けど力になれることがあるようならいつでも言ってこいよ。何でもいいから」
「何でも……その方がお前の気持ちが軽くなるのなら」
「だから、俺のことがどうこうより、自分のためにって考えろよ」
「分かった。だがそれを要求しようにも、お前の連絡先を知らないのだが。個人的なことで氷帝に電話をかけるわけにもいかないだろう。都合が悪くなければ、何かしらの連絡先を交換しないか」
そういえばそうだったと跡部も思い出す。散々悩んだことだったのに、こうして直接話せたことで頭から抜け落ちてしまっていた。「構わないぜ」と跡部はポケットから携帯端末を取り出す。幸いにも、今日持ってきているのは友人用の端末だ。今日からここに手塚が加わるのかと思うと気持ちが落ち着かない。
ふと前を見やると、同じように携帯端末を手にした手塚が、困ったように画面を覗き込んでいた。
「……跡部、すまない。やり方が分からないんだが」
まるで世界の終わりとでも言うような声で呟く手塚に、跡部は目をぱちぱちと瞬いた。連絡先を交換したいと言いながらやり方が分からないとは、何とも間抜けなものである。跡部は肩を震わせて笑った。
きっとそこには家族や青学のメンバーの連絡先くらいは登録されているのだろうが、相手主導でやってもらったに違いない。
それほどに慣れていないのだろうなと思うと、その数少ない登録先に自分を加えてもらえるというのが、やはりどうにも気分を落ち着かなくさせた。
「貸してみな」
バツが悪そうにしている手塚から端末を受け取る。画面もデフォルトのままのそれが手塚らしいと、口許に笑みが浮かぶ。背景を氷帝の校旗にでもしてやったら面白いだろうなと思いつつも、大人しく連絡先の相互登録だけにしておいた。
「ほらよ」
「ああ、すまないな。ありがとう」
「手塚、本当に……試合、出られるんだよな」
手塚に端末を返しながら、跡部は再度確かめる。
激痛を耐えた男は、勝つためなら不調を隠してでも試合に臨むかもしれない。
手塚の率いる青学と勝負したいのは確かに本音だが、この先のテニスをつつがなくできるようにと祈っているのも心の底からの本音だ。
「肩は治ったと言っただろう。全国大会に支障はない。氷帝とも、準々決勝で当たるな」
当たる前に敗退するとは欠片も考えていない手塚に、跡部はホッとした。
「楽しみだ」
そう続けた手塚に、目を見開く。言葉と表情が少しも一致していないが、こんなことで嘘を吐く男ではないと思いたい。本当に全国大会に出られることを嬉しく思い、そして楽しみにしているらしい。
氷帝の出場についてまだ少しプライドが邪魔をして、純粋に喜べていなかった跡部は苦笑した。
気持ちの上で手塚に負けたくはない。自分も高みを目指して力を付けようと、拳を握りしめた。
「俺も、楽しみにしてるぜ、手塚」
そう返すと、手塚はこくりと頷く。そうして、携帯端末を見下ろしたまま動かなくなった。何かを言いあぐねている様子が気にかかり、「手塚?」と呼んでみる。
「さっき……力になれることがあるならと言ったな。何でもいいのか?」
「あ? ああ、こっちでのリハビリ施設でも見繕ってやるか? それともジムの方がいいか。体力もちょっと落ちてんだろ。英気を養いたいってんなら、俺が最高のプランを考えてやろうじゃねーの」
手塚が望むならば、何だって叶えてみせる。関係がない、責任などないと蚊帳の外に置かれるよりよほどマシだ。
遠慮深い……というより本心で厚意を跳ね返してくる手塚が、何を望んでくれるのだろう。どうしてだかそわそわと落ち着かない気分になるのを必死で抑えて、いつものように笑ってみせた。
「いや、そういうことではなく……」
「なんだよ、俺様に叶えられないことがあると思ってやがんのか?」
「本来なら、頼むようなことではないと思う。望まないかもしれない相手に言って叶えたところで、それが本当に叶ったと言えるのかどうか」
「俺に哲学でも説きたいってんじゃなきゃ、さっさと言え手塚」
まどろっこしいとやんわり責めてみれば、意を決したように手塚が顔を上げる。まっすぐ見つめてくる瞳は、あの日のような熱さをたたえていて、ほんの少し胸が跳ねた。
「俺はまたお前とテニスがしたい」
目を瞠る。
お前と、テニスが、したい。
手塚の声が頭の中で響いて全身に染み渡り、留まっているように思えた。
「……俺と?」
「ああ、お前とだ。公式戦でなくても構わない。時間の都合がつけば、今からでもいいんだが」
手塚との再戦を望んでいる跡部にとってそれは願ってもないことだが、何を考えているのだろう。
「頭沸いてんのか?」
「いや、沸いてはいない」
至極真面目に返されて、出端をくじかれたような気分を味わうが、ここで勢いを削がれていてはいけない。跡部は一歩踏み込んで、息を吸い込んだ。
「どこの世界に! 怪我のきっかけになった相手とうきうきゲームしたがるヤツがいるんだよ!」
「ならば世界初かもしれんな」
うきうきというよりうずうずだが、と続ける手塚に毒気を抜かれ、跡部は項垂れて額を押さえた。
表情に出ないからか、本当に何を考えているか分からない。いや、この男はテニスのことしか考えていないのではないだろうか。
強い相手とゲームがしたい。それは自身のモチベーションや技術の向上につながり、損はないはず。
だがよりにもよってこの俺を選ぶのか? と眼力(インサイト)で探ってみるも、やはり読み切れない。
「……俺とお前は準々決勝で当たるだろうが。敵同士だぜ。まさかテメェ、俺とゲームしながらデータでも盗むつもりじゃねえだろうな」
「……なるほど。確かにそういうことも可能だろうが、それは俺自身もお前にデータを取られるリスクがあるということだ。お互い様ではないのか」
「誰がテメェにデータなんか取らせるかよ」
「なら問題はないだろう。……お前が俺とは打ちたくないという思いがあるなら、仕方ないが」
「いやそんなわけねえだろ。どこからそんな発想が出てくるんだよ、アーン? 俺はお前のプレイ好きだぜ。予想外に強引で傲慢なアレを打ち負かすのを想像すると楽しいな」
手塚が言いあぐねていた理由が分かった。肩の怪我を引き起こしたということを気にして、相対するのを忌避したがっているのではないかと思ったらしい。
確かにそんな相手を無理やり引っ張り出しても、望みが叶ったとは言い難いだろう。
しかしながら、まったく馬鹿げた思考だ。手塚国光とプレイしたがっている男がどれだけいると思っているのだろうか。
「傲慢……そんなことは初めて言われた」
「そうかよ? だが頂点に立つ者には必要な要素だろう。自分は周りを引っ張っていくべき立場、自分にしかできないっていう自信は、プレイにも現れる。褒めてるつもりはねえが、貶したわけでもねえんだぜ」
彼のプレイは、いっそ小気味よいほどの強引さを見せる。
部長なのだからという立場以前に、己の持つ力ならば当然だとでも言いたげな傲慢さも、跡部にとっては気持ちの良いものだった。
跡部自身にも、覚えがあるものだからだ。
跡部の場合分かりやすくパフォーマンスに換えているというだけで、立場も気概も、手塚と同じ。
それを、あの試合の中で初めて知った。思い出すだけで体が熱くなってくる。
「……跡部、やはり今からテニスがしたい」
やはり強引で、傲慢で、貪欲だ。表情こそ変わらないものの、負けず嫌いなのだろうことが分かる。同じくあの試合を思い出して、熱くなったのだろう。
「俺様は制服なんだが」
手塚は青学のジャージを身に纏っているし、ラケットバッグも担いでいる。まるで最初からテニスをしにきたかのようだ。だが跡部は制服のまま。靴だって革靴で、テニスをするには向いていない。手塚と打ち合えるのは僥倖(ぎょうこう)だが、これではいつもの力を出せやしない。
「何でもいいと言ったな?」
次の機会にと暗に言ったつもりだが、手塚には通用しなかった。
跡部としても、この機会を逃したくはない。いくら連絡先を交換したからといっても、まさか毎日連絡を取り合うような仲にはならないだろう。敵同士なのだし、今日を逃したらいつ次の機会とやらが巡ってくるか分かったもんじゃない。
跡部はしばし考え込み、自身の家で管理しているテニスコートを貸し切るかと電話をかけた。
幸いにもすぐに使えるところがあり、ここからもそう遠くはない。施設の責任者に礼を告げ通話を終えると、手塚がわずかに驚いたような顔をしていた。
「なんだよ?」
「まさか、貸し切りとは思わなかった。お前が跡部だということを忘れていたな」
呆れてもいるようで、跡部は少し眉を寄せる。自身に対して「跡部家の御曹司だということを忘れていた」なんて面と向かって言い放つ男は珍しい。それは誇りでもあるのにだ。
「ハ、テメェが万が一肩の怪我で無様なプレイしてもギャラリーに見られないようにっていう俺様の配慮だぜ」
「余計な世話だが」
「冗談だ」
ピリ、と空気が凍てつきそうなほど、鋭い視線が向かってくる。
冗談だと返してはみたものの、二割くらいは本心だった。
九州から戻ってきたばかりならば――しかも恐らく直接来たのだろう状態では、まともなプレイができないかもしれない。
もし、万が一のことがあった時、自分ならば見られたくない。どこからチームの仲間に伝わって、大会に出られなくなるか分からないのだから。
その時に傍にいるのが自分だけならば、どうにでもできる。手塚の望むようにしてやれる。
そんな若干贖罪めいた思いが後ろめたくて、視線を逸らす。変なところで聡い手塚は気づいただろう。短いため息が聞こえた。
「俺の肩のことは気にするなと言ったが、お前に貸しができたのだとでも思えば、なかなか愉快だな、跡部」
「アァン!?」
「冗談だ」
仕返しのつもりか、手塚は間を置かずにそう返してくる。口許にほんのわずかの笑みをたたえてまでだ。
二の句が継げずに絶句して、跡部は手塚を睨みつけた。
「テメェ、いい性格してるじゃねーの」
「褒め言葉か?」
「褒めてねーが!? まさかこういうヤツだったとはな……読み切れなかったぜ……」
まったくおかしな男だと顔を覆い、瞳に力を集中させる。御曹司だということを忘れるどころか、仕返しとはいえ跡部景吾をからかおうなんて輩がいるとは思わなかった。
「まあいい。おら、行くぞ手塚ぁ」
「ああ、楽しみだ」
釈然としないままではあるが、跡部は手塚と連れ立って近くの屋内コートへと足を向けた。
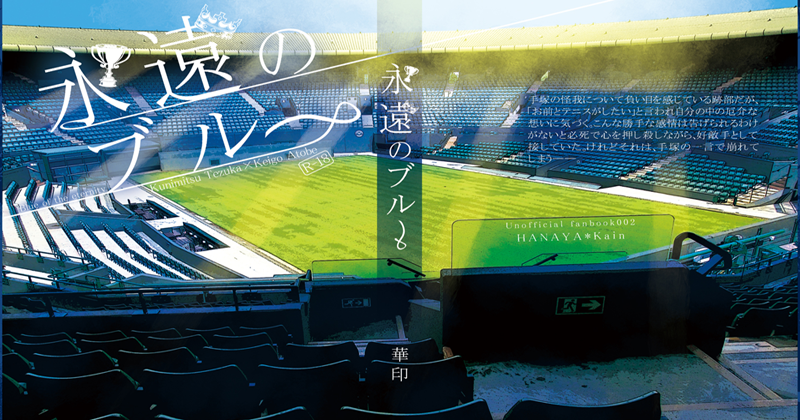
コメント