「ここにはよく来るのか?」
「あ? ああ、まあな。運営の視察がてら」
そういうところは都内にいくつかある、と預けているラケットをくるりと回しながら答える。当然ウェアも跡部のものだ。レンタルもあるが、ウェアはともかくラケットは自前のものでないと手塚とは打ち合えない。
手塚もジャケットを脱いで、ストレッチをすませたようだ。
あの日以来の邂逅だ。どうしても気分が高揚してくる。
「セルフジャッジ、ワンセットマッチだ」
「ああ、構わない。跡部、手加減はなしだ」
ネットを挟んで対峙する。まるであの日の続きのようだ。サービスは跡部から。ドクンと心臓が鳴った。
手加減はなしだと言われたが、今の手塚の状態が分からない。
肩は本当に大丈夫なのか。そうでなくてもお互いが大事な試合を控えているのに、全力でいくわけにはいかないだろう。手の内を晒してしまうという意味でもだ。
跡部はトスを上げ、まずは様子見だと球を打った。
だがそのボールは、一瞬のうちに跡部の足元を撃ち抜いた。憎たらしいほど鮮やかなリターンエース。
「油断しているお前が悪い」
そんなことをのたまう男が本当に憎たらしい。
「確かに手加減なしでいいみてぇじゃねーの! 手塚ァ!」
手塚の打ったボールを、今度は全力で打ち返してやる。手塚はそれに追いつけず、跡部はニヤリと口の端を上げた。グリップを握り直して構える手塚も、ほんのわずか、口許が緩んでいる気がした。
「そうこなくてはな、跡部」
打つ。拾われる。叩き返す。迎え撃たれる。長いラリーになった。
パァンと響くインパクト音と、床とシューズがこすれる音。ボールは互いの間を何度も行き来し、ポイントが取れない。ラリーをしようと思ってしているわけではない。返されるから、打ち返してやる。
なんであれが決まらないんだ! と舌を打ちたいが、そんなことをしている間に足元を撃ち抜かれる。気を抜けない。それは手塚の方も同じらしく、跡部が手塚の打球を捉えた瞬間わずかに眉が寄る。返される予定ではなかったとでもいうようにだ。
「……っくそ」
だが手塚が打ち返してきたボールにわずかに追いつけず、点が取られる。流れた汗を拭い、ネット越しに睨みつけてみた。
「次は俺が取るぜ」
「俺は負けない」
「だからそういうところだっつってんだよ!」
少なくとも昨日までリハビリを受けていた男とは、とても思えない。手加減なんてできやしない。
打球が手塚の足元を撃ち抜く。どうだ、としたり顔でラケットの先端を向けて挑発すれば、気分が良い。
だが跡部は気がついていた。手塚からポイントを取った瞬間以上に、自分の打球を手塚が捉えて返してくる瞬間が楽しくて仕方がないことに。
本気で打ったそれを、返してくる男がいる。ネットを挟んでそこに在るということが、何よりも嬉しい。手塚が本気で打っただろうボールを、全力で返すことができる。それが、どうしようもなく楽しい。
このラリーがいつまでも続けばいい。終わりたくない。終わらせたくない。
あの日はどれだけタイブレークが続いても構わないと思ったが、その時の感情とは少し違うように思った。
――――俺の打球を手塚に返してもらいたい。手塚の打ったボールは絶対に返したい。何度でもだ。
ポイントを取らなければならないというのに、それでは勝負がつかない。打ち負かしたいという確かな本音の傍らで、このままずっと打ち合っていたいという思いがくすぶる。
気がつけば、打ち合い始めてから二時間が経過していた。
「手塚ァ! そろそろバテてんじゃねーのか!」
「お前こそ、スピードが落ちているぞ、跡部」
「抜かせ!」
煽るような指摘には逆に火がついて、全力でラケットを振り抜く。速度を上げた打球は手塚のラケットが捕まえる。
「……っ」
だが、受け止めきれずにボールごとラケットが宙を舞った。わずかなうめきが耳に届き、跡部は息を呑む。
「手塚!」
すぐさまネットを飛び越えて駆け寄り、手塚の腕を案じた。
「今の変な打ち方しただろ。痛みはあるか? すぐ医者に」
「いや、問題ない。少しタイミングを誤っただけだ」
「本当にか? 欠片でも嘘が混じってやがったら、許さねーぜ。俺はお前の下についてるヤツらじゃねえんだ。意地張ってねえで、俺にだけは本当のことを言え」
頂点に立つ男は、下の者に弱みを見せてはならない。それはそのまま士気に直結するからだ。責任感が強く頑固な手塚が、痛みを隠す可能性は充分に考えられた。
「……本当のことを言っている。お前相手に遠慮したところでどうにもならないだろう」
それはそうだが、とあの容赦ない打球を思い起こして言葉に詰まる。
あの日のように、左腕は震えていない。手塚の言っていることは本当なのだと分かる。分かるが、怖い。
打ち合っている間は打ち負かすこと以外何も考えないのに、こうしてラケットを下ろして向かい合うと、途端に怖くなる。
自分の打球が、今度こそこのプレイヤーを殺すかもしれない。またあの激痛を味わわせるかもしれない。
いや、たとえ相手が自分でなくとも、いつ壊れるか分からないという爆弾を抱えてしまったのだ。自分が、抱えさせてしまった。
「跡部、俺は平気だ」
その罪悪感を感じ取ったのか、手塚は静かに、だが力強くそう告げてくる。
跡部は眉を寄せ、じっと手塚の左肩を見つめた。
そうしてめいっぱい躊躇ってから口を開く。
「触れてもいいか?」
「ああ」
跡部の躊躇いに手塚は何でもないように頷いてくれる。跡部はゆっくりと左手を上げ、指先でそっと肩に触れる。痛みは本当にないようで、息を呑む音は聞こえない。手のひらで肩を包んでもだ。
跡部は心の底からホッとする。
近づいた距離をさらに縮めて、手塚の肩に置いた自分の手に額を乗せた。この重みもどうやら平気のようだ。
そっと手を抜き、腕のラインをなぞる。ウェア越しに伝わってくるのは人としての体温で、熱くも冷たくもない。
――――ちゃんと、動くんだな。
肩に額を乗せたまま、腕を下りていく自身の指先を眺める。それは手首にまで到達した。強く握られているラケットに、爪の先が当たる。
はあぁ……と長く息を吐いて、小さく、本当に小さく「よかった……」と呟いた。
「俺様としたことがつい熱くなっちまったぜ……。今日はもう切り上げるぞ、手塚。二時間以上も打ってりゃテメェも満足しただ、ろ……」
体を起こしてそう提案してみる。何ともないとはいえ、いきなり跡部クラスのプレイヤーと全力で打ち合い続けるのはよくない。
次の機会でもいいわけだしと振り向けば、思ったよりも近いところに手塚の顔があって驚く。
ややあって、手塚は少しずれた眼鏡を押し上げて低い声で返してきた、
「五―四でお前がリードしている状態だな」
「そこは目を瞑れよ。お前のためを思って言ってやってんだろうが」
どうも負けたままなのが納得できないらしく、跡部は呆れ果てる。公式戦ではないのだから、勝ち負けよりも肩のことを気にしてほしい。
「次は今の続きからすればいいだろ」
「次……そうだな。だが俺は負けない」
「言ってろ、勝つのは俺だ」
次があるということで手塚を納得させ、タオルで汗を拭う。だけどもう少しだけ自主トレをしていくつもりでグリップを確認していたら、すっかり帰り支度を調えた手塚が歩み寄ってきた。
「お前は帰らないのか」
「ああ、もう少しだけな。気をつけて帰れよ手塚」
「今日は付き合わせてしまって悪かったな。だが、いいプレイができたと思う」
「そりゃ何よりだ」
こちらの台詞だと言ってやりたかったが、ここは素直に受け取っておこう。跡部は肩を竦めて口の端を上げた。
「跡部」
だがまだ何か言い足りないようで、手塚はじっとこちらを見据えてくる。「なんだよ?」と怪訝そうに見返してやれば、躊躇うような様子を見せた。
「俺は言葉にすることが不得手だ。しかし、やはりちゃんと言っておかなくてはいけない」
神妙な面持ちに、ドキリと胸が鳴る。悪い方向に考えてしまうのは、もう仕方がない。
「お前には感謝している」
「…………アァン?」
なんだって? と訊き直したい。手塚は今なんと言ったのだろうか。
跡部は怪訝に歪めた顔をさらに不審げに傾げ、いったい何の冗談だと目を細めた。
「何を寝ぼけたこと言ってんだ、手塚ァ。俺はお前に恨まれる覚えはあっても、感謝される覚えはこれっぽっちもねえぞ」
「お前とのあの試合、俺に取っては無二のものだ。自分があれほどまでがむしゃらになれるとは思わなかった。お前が全力で向かってきてくれたからだろう、跡部」
目を瞠った。
同じ気持ちでいるだろうとは思っていたが、当人に明確に言葉にされるなんて考えてもみなかったことだ。
「俺はまだ、上を目指していける。ここで立ち止まっていたくない。そう思わせてくれた。相手がお前でなければ、俺はどこかで諦めていただろう。負けたくない、最高のプレイがしたい。それに応えてくれた」
胸の中にあった言葉が、そのまま音にされているような感覚を味わう。それはこちらが言いたかったことだ。
まだ上を目指せることを、まだ上を目指したがっていることを、ネットを挟んだ対戦者が気づかせてくれた。
「だから俺はお前に礼を言わなければならない。あの日の試合は、お前でなければ駄目だっただろう」
自分の呼吸さえ聞こえてこない。手塚の声しか耳に入ってこなくて、体と魂が別々になってしまったかのように感じた。
「お前と試合ができて良かった、跡部。お互いの都合が合えば、また打ち合おう」
そう言って出口へと向かっていく手塚の背中をただ茫然と見送る。
完全に姿が見えなくなった途端、急激に体の熱が上がって、現実に引き戻された。
――――待て。
カアッと火照ったのは体ばかりでなく、頬も熱く朱が広がった。
――――待て、ちょっと……待っ、ち、やがれ、なんでだ!
跡部は叫びかけた口許を左手で覆い、唐突にせり上がってきたひとつの感情に大いに混乱する。
『お前でなければ駄目だった』
手塚の声が頭の中で繰り返される。何度も、何度も。
そのたびに頭が沸騰しそうなほどの熱さが加わって、爆発寸前だ。心臓はうるさく騒ぎ立て、視線が定まらない。
そんなわけがない。そんなわけがないのだ。
あの男はライバルであって、それ以下ではないし決してそれ以上であってはならないのに。
――――違う、違う違う、絶対にだ!
特別な相手ではあるが、まさか、そんな。
好きだなんて、そんな。
跡部は混乱したままボールを高く放り投げ、
「――んなことあるわけねえだろうがぁ! てづ……っかァ!!」
そして、盛大に空振った。
うっかり名前を呼びかけただけで動揺するなんて。ラケットを持ったまましゃがみ込む。打てなかったボールがコロコロと床を転がっていく。顔の熱はまだ引かず、むしろより一層上がったような気さえした。
――――待てよ、違うだろ、あり得ねえ! あれはアイツがっ……珍しくよくしゃべるからだ。しかもガラにもねえことをべらべらと!
珍しいと思うほど交流もなかったが、寡黙であることは知っていた。言葉にするのは苦手だと本人も言っていたように、気さくに話すような男ではない。
それが、あんな言葉を吐いてくるから、脳が混乱しただけだ。そう思いたい。
――――アイツも俺と同じように思ってたことは嬉しいっていうか、いや違う、安心だ! 俺だけが特別に思ってるなんてフェアじゃねえからな! テニスに懸ける本気の思いが同じで……もっと上を目指せるっていう貪欲さが同じで……それがただ嬉しいってだけだろうが! なんでっ……。
なんで、こんなに心臓が騒がしいのだろう。
ドキンドキンドキン。
熱は引いていかない。
ドキンドキンドキン。
おかしな思考を散らそうと、目を瞑ってぶんぶんと首を振ってみる。
目蓋の裏に、あの男の顔が浮かんできて、逆効果だった。
「あぁくそッ……あり得ねえ……!」
この胸のむずがゆさを、認めたくない。
跡部は少し汗で湿った髪をがしがしとかき混ぜて、唸りながら頭の中を整理する。ゆっくりと息を吐いて、立ち上がり、息を吸い込んだ。
「俺様を混乱させるとはやるじゃねーの」
大会前に結構な策を弄してくれるな、と目を見開き、もう一度高くボールを放った。
手塚にそんな真似ができるとは思っていない。言葉以上の意図がなかったとしても、事実跡部は盛大に困惑して、混乱している。
だが。
「勝者は……俺だ!」
今度こそ落ちてきた球を打つ。全身全霊を込めたその打球は、幻の手塚をすり抜けてライン上を撃ち抜いた。
次のページはちょっとえっちなとこです。↑とはつながってません。
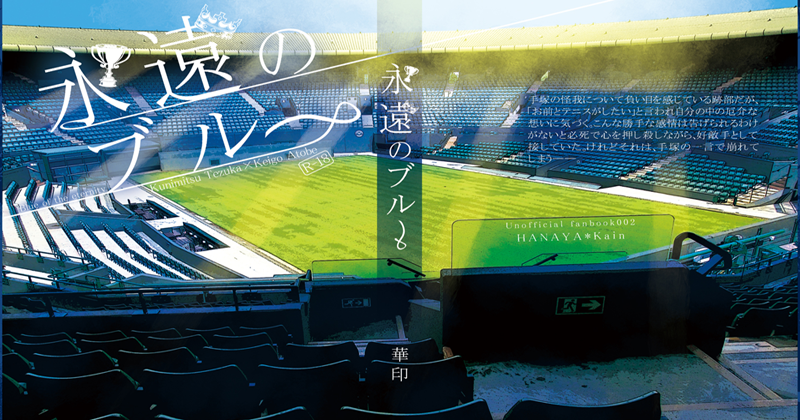
コメント